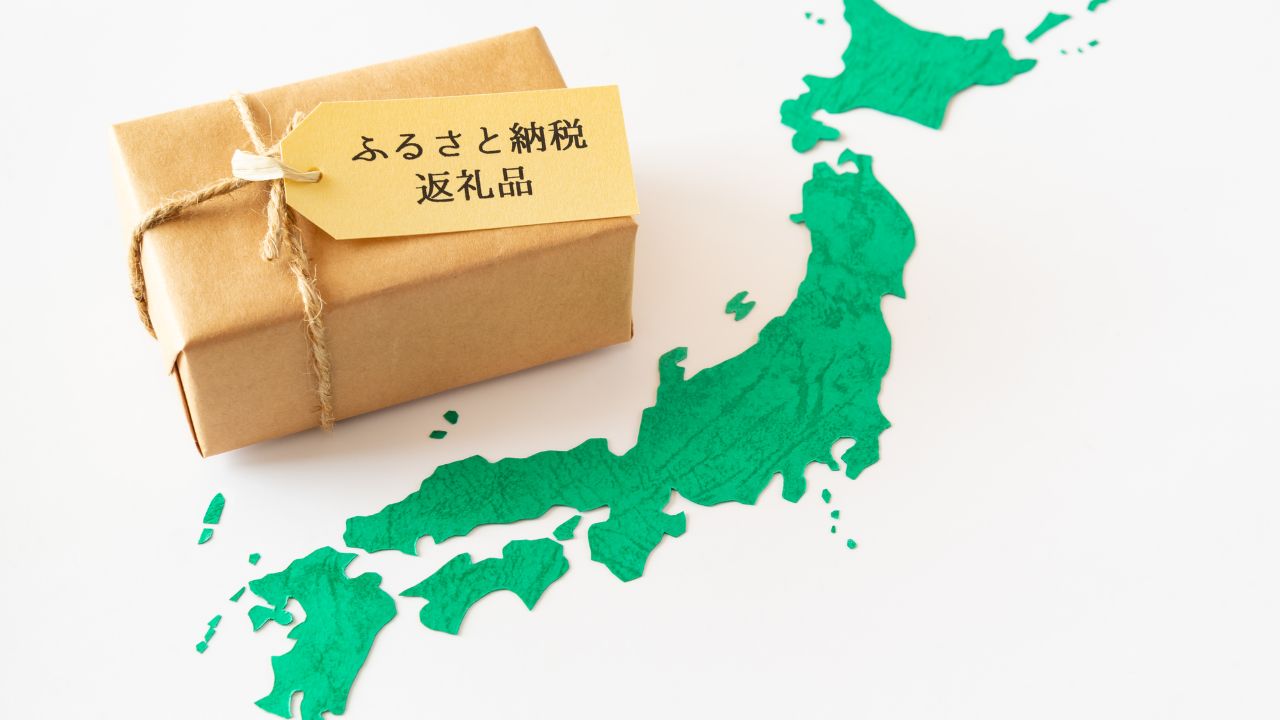
目次
長引くゼロ金利時代が終わり、世は「金利ある世界」へと移行しました。金利上昇やインフレは、一見すると不動産投資にとって逆風に思えるかもしれません。しかし、実はこの経済状況こそ、レバレッジを効かせた「新築アパート投資」が真価を発揮するチャンスです。インフレが借金の実質的価値をどう変えるのか?金利上昇を上回る家賃収入を得る戦略とは?一歩先の金融知識で、時代を味方につける資産形成術をご紹介します。
大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
「こんなに払ってたの…?」年収3,000万円の“リアルな手取り”と税金の重み
給与明細から見る所得税・住民税のインパクト
年収3,000万円の方は、累進税率の影響もあり、かなりの金額の所得税・住民税を負担しているでしょう。具体例として、賞与を年2回(2か月分×2回)と仮定し、残りを12か月で均等に支払う場合、月給の額面は187.5万円となります。ここから天引きされる税金は、所得税が約37万円、住民税が約21万円に上ります。
意外と知らない社会保険料の負担
給与から引かれるものは税金だけではありません。健康保険料と厚生年金保険料、従業員の場合には雇用保険料も負担しなければなりません。地域や保険組合によって多少変わりますが、合計で約14万円が月給から差し引かれます。
ふるさと納税、iDeCo…メジャーな節税策の「上限」と「限界」
年収に応じた控除額の上限を再確認
税金や社会保険料の負担感が大きい高所得の方々を中心によく利用されているのが、ふるさと納税やiDeCo等の節税策です。しかし、これらの節税策にも、「上限」があるという弱点があります。ふるさと納税は、給与所得で年収3,000万円の方の場合、自己負担額の2,000円を除いた寄付金額全額が控除される上限額は、100万円前後になることが多いです。iDeCoについては、掛け金に上限が設けられており、2025年時点では会社員の上限は年間24万円か27万6千円で、予定ではありますが、2027年に引き上げられて、年間74万4千円になる見込みです。
あくまで「控除」であり、所得を大きく動かすものではない
これらの節税策は金額に上限が設けられており、高所得者にとっては対策として不十分になる場合があります。また、これらの節税策は、寄付金控除や、小規模企業共済等掛金控除等の制度の枠組みであり、税制上は「所得控除」として扱われます。住宅ローン控除のように所得制限で適用が決まる制度では、合計所得(所得控除前の金額)で判断されることがあります。この場合、所得控除による節税を行っていても、その効果が反映されない点が重要です。
なぜ儲かっても赤字になる?不動産投資の節税マジック「減価償却」
「帳簿上の赤字」を作り出し、給与所得と損益通算する仕組み
建物部分の価値は年々減少すると見なされ、その分を経費として毎年計上できるのが減価償却です。「実際のお金」(キャッシュフロー)は、家賃収入から固定資産税等の経費や借入金の返済額(元金+利息)を引いて残った金額です。一方、「帳簿上の利益」は、家賃収入から経費と減価償却費のみを引いて計算します。(注:借入金の元金返済額は引きません)この「帳簿上の利益」と「実際のお金」の差を利用して、手元に現金を残しつつ、「帳簿上の赤字」を生み出すことができます。
なぜ「中古」ではなく「新築」の、特に「木造アパート」が減価償却で有利なのか
減価償却費は、建物の購入価格と耐用年数で計算されます。中古の場合は新築よりも耐用年数は短く計算されます。物件によっては4年間で減価償却が終わり、その後は「帳簿上の利益」が黒字になるケースもあります。一方で新築の場合は22年以上の期間で減価償却を計算するため、長期間安定して「帳簿上の赤字」を生み出すことができます。また、この耐用年数は、建物の種類や用途によっても変わります。木造アパートの場合は新築で22年ですが、RC造のマンションであれば新築で47年です。長すぎると1年間の減価償却費の金額も小さくなり、「帳簿上の赤字」にならず、節税のための不動産投資には向かないため、注意が必要です。
節税だけじゃない!インカムゲインと資産形成を両立する「新築アパート」の優位性
節税効果を得ながら、安定した家賃収入(インカムゲイン)も確保
新築の木造アパートであれば、減価償却の期間が22年であり、「帳簿上の赤字」を安定して生み出しやすいです。また、不動産投資において、当然家賃収入が安定するかどうかも見逃せません。中古物件と比べて空室リスクも低く、安定したキャッシュフローが期待できます。
最新設備で入居者を集めやすく、資産価値が落ちにくい
新築の物件は、最新の設備やトレンドを取り入れた設計が可能であり、より市場競争力が高くなる傾向にあります。それにより、入居者の集客率向上、空室率の低下や家賃の下落抑制が期待でき、当面の間資産価値が維持されやすいというメリットがあります。
金融機関からの評価も高く、融資戦略が立てやすい
新築アパートは、中古物件等と比較して、金融機関からの担保としての評価が高く、融資を受けやすいという特長があります。物件や条件によってはフルローンでの資金調達が可能になるケースもあり、レバレッジを効かせて投資を実現するには、非常に有効な選択肢でしょう。
<執筆>
西口 孟志
西口孟志税理士事務所 税理士
1994年1月30日生まれ。京都府出身。 同志社大学経済学部卒業後、日本電気株式会社に入社。 その後、EY税理士法人等の複数の税理士法人にて、個人事業主から上場企業まで幅広く税務会計の支援に従事。 2022年に京都市にて、西口孟志税理士事務所を開業。


