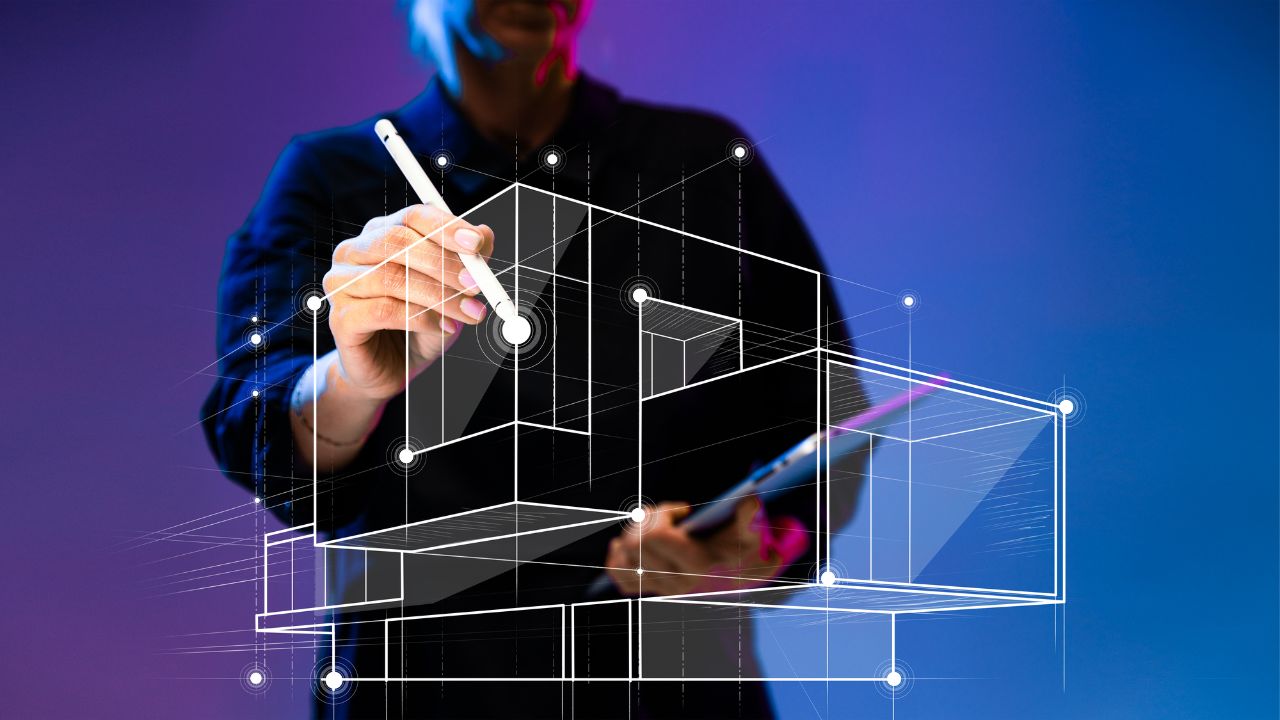
目次
NISAやiDeCoなどの積立型投資がブームとなっていますが、これらのような金融資産に偏重したポートフォリオ(資産構成)では、インフレや市場暴落の際に思わぬ脆弱性が露呈する恐れがあります。どんな時代にあっても安定しているのは実物資産、すなわち「不動産」です。その中でも「新築アパート」は収益性に定評があり、多くの高所得者層が自らのポートフォリオに組み込んでいます。なぜ高所得者層の資産防衛に実物資産である新築アパート投資が不可欠なのか、金融資産との違いを比較しながら、その役割と魅力を基本から解説します。
大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
あなたの資産は大丈夫? “金融資産依存”に潜む3つのリスク
日銀によるマイナス金利政策の解除から1年半が経過しましたが、その成果はどのようなものだったでしょうか。あなたの預貯金通帳をのぞいてみてください。これまで影の薄かった利息の額がほんの少し増えていることがわかります。これは日本経済が上向きに転換していく兆しなのかもしれませんが、「老後の暮らしは預貯金で」と安心できるほどの額には達していません。そもそも、預貯金積立の源泉となる給与のベースアップが金利や物価の上昇に追いついていないのですから、景気好転など実感できなくて当然です。
インフレ真っ只中にある日本においては、今後も大切な資産を守り増やしていくための知恵を絞ることが重要です。その手始めに、金融資産に関わる「インフレ・3つのリスク」について知っておきましょう。
リスク① インフレによる「現金価値」の目減り
インフレ時は現金の価値評価が下がります。「昨年は100円で買えた品物が今年は200円に値上がりしている」といった話を最近あちこちで聞きます。これはすなわち「現金100円」の価値が1/2に目減りしてしまったということです。
リスク② 経済混乱による「株式」の大暴落
インフレになると、株式の将来利益を現在価値に反映する「割引率」が上昇するため株価は下落します。それと並行して中央銀行(日銀)による金利引き上げが行われれば、赤字を避けたい投資家による売り注文が殺到し、株価は大暴落します。
リスク③ 為替変動による「海外資産」への悪影響
直近(2025年9月15日時点)の円相場は1ドル=146~148円程度で推移しています。1年前は140~143円、半年前は150円を超えた時期もありました。特にインフレ時は外国為替の変動幅が大きくなりがちで、円相場によっては海外資産の価値が下落する「為替変動リスク」に陥ります。
徹底比較!「金融投資」と「実物投資」とは何が違うのか?
金融資産に該当するのは現金・預貯金・株式・投資信託・NISA・債券・貯蓄型生命保険・iDeCoなど。一方、実物資産に該当するのは不動産・貴金属・美術品などです。前述の通り、金融資産に依存しすぎるとリスクは高まります。では、実物資産である不動産はどうでしょう。国内不動産においては、それほど大きな資産価値の変動は起こりませんし、家賃収入は株価のように短期間で乱高下することはありません。株式の主な収益は「売買差益(キャピタルゲイン)」ですが、不動産の主な収益は「家賃(インカムゲイン)」です。
株式投資は1株単位で購入することができ、購入金額も不動産と比較すれば少額ですが、100~1,000株程度購入しないとまとまった利益は得られませんし、株式購入には自己資金(現金)が必要です。一方、不動産購入にはローンを活用してレバレッジを効かせることができるので、自己資金が少なくても高額不動産の購入ができます。そこでお勧めしたいのは、複数戸から家賃収入が得られ、外装・内装ともに最新設備を網羅した新築アパートへの投資です。
なぜ不動産投資の中でも「新築アパート」がポートフォリオに加えやすいのか?
新築アパートへの投資をお勧めする理由の一つは「ローン審査の通りやすさ」です。不動産には法で定められた耐用年数があり、新築からの経過年数で評価額が減価されます。木造建物の耐用年数は22年、鉄骨造で19~34年(骨格材の肉厚により異なる)で、これらの残余年数が長いほどローン評価は高くなり、新築であれば当然、購入当初の評価額が減価されていないためです。
加えて、耐用年数の残余年数が長ければ長いほど確定申告で減価償却(=購入代金の経費計上)できる年数も長くなります。毎年高額な家賃収益を得ていたとしても、これらの経費計上により大幅な節税が叶うのです。さらに、築5年から10年も経つと、競争力を維持するために内装・外装を最新設備へ入れ替えるリフォームが一般的になります。これらの費用も経費に組み込むことができます。
年収3,000万円世帯の理想のポートフォリオを考える
資産運用にはリスクヘッジが欠かせません。株式などの“攻め”の金融資産、不動産などの“安定”の実物資産へ分散投資していくことが賢明です。ただし、自己資金の全額投資は日常生活での突発事態(事故や病気等)に対応できなくなるリスクがあるため、ある程度の現金や預貯金は手元に残しておくことをお勧めします。
ライフステージに合わせた投資配分の見直しも必要です。30~40代はリスクを恐れず金融資産投資をメインに行い、50代以降は不動産を中心とした実物資産投資へと移行していくといったスタイルが理想的。あるいは、結婚・子供の誕生や進学・マイホーム購入といったタイミングでも見直しを行う必要があるかもしれません。


