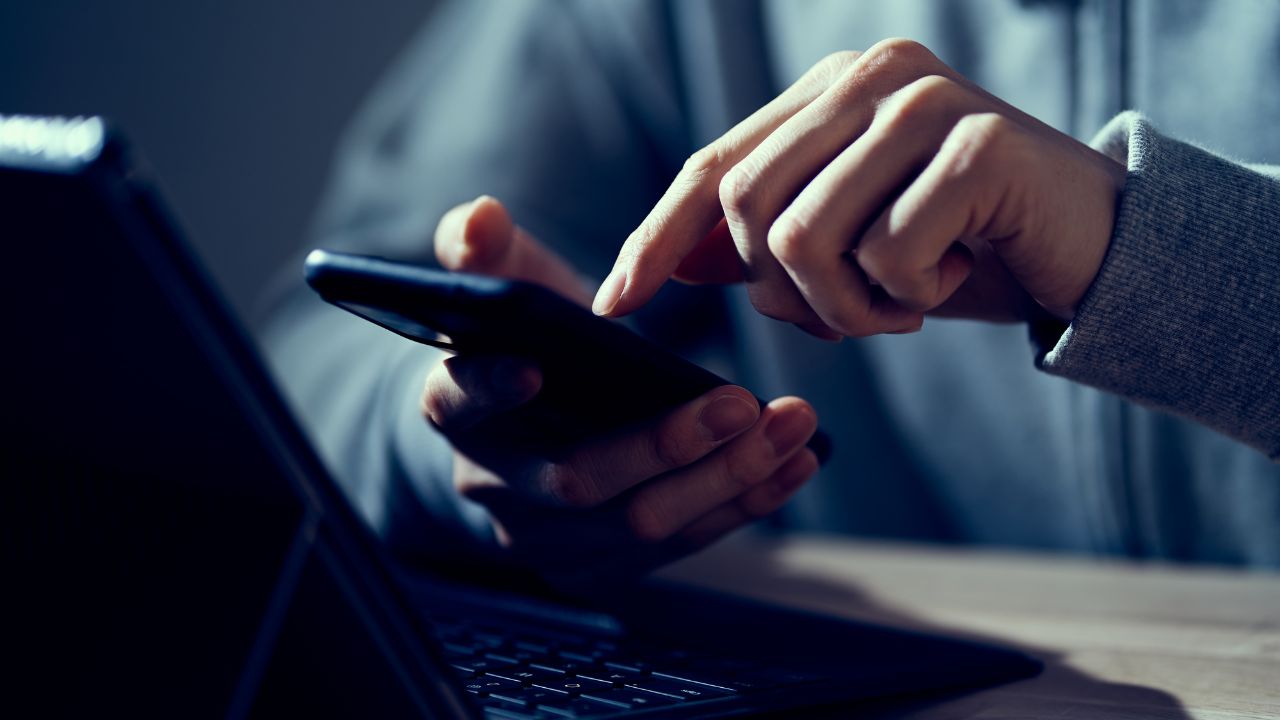
目次
物件の評判を入居希望者がSNSで検索する時代。もし心ない入居者が物件名や大家を名指しで誹謗中傷したり、虚偽の情報を拡散したりした場合、オーナーはどのようなリスクを負うのでしょうか? 放置すれば空室リスクに直結しかねないSNSトラブル。投稿の削除請求は可能なのか、損害賠償を請求できるのか、弁護士が具体的な法的措置と予防策を解説します。
大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
アパート経営を揺るがす「デジタル評判リスク」とは?
今や入居希望者は、物件を内見する前に「アパート名+口コミ」で検索するのが当たり前になっています。その際に目に飛び込んでくるのが、SNSや口コミサイトに書き込まれた入居者の声です。たとえば「隣人の騒音がひどい」「ゴミ出しマナーが悪い」「設備に欠陥がある」など、時には根拠のない虚偽の情報や、感情的な誹謗中傷が書かれることもあります。こうした投稿が拡散すれば、「あの物件は住みにくい」というレッテルが瞬く間に広がり、入居希望者が敬遠する事態に直結しかねません。
さらに怖いのは、悪評を放置した場合の連鎖的な影響です。新規の問い合わせが減少するだけでなく、既存の入居者も不安を感じ退去を検討し始めます。その結果、空室率の上昇や賃料下落につながり、最終的には物件の資産価値が大きく毀損されることになります。物件経営において「評判」は数字に直結する資産そのものといえるのです。
こうした時代にオーナーに求められるのが、「評判マネジメント」の視点です。単に建物を維持管理するだけでなく、デジタル空間における物件の評価を意識し、悪評が拡散した際には早急に対処する姿勢が欠かせません。法的措置を取る前に、管理会社と連携して事実確認や入居者対応を行うことも重要です。アパート経営の安定性を守るためには、現実の管理と同時に“ネット上の管理”を意識することが不可欠といえるでしょう。
「悪評の削除」はどこまで可能か?弁護士が教える法的ステップ
SNSや口コミサイトに掲載された悪評を「削除したい」と考えるのは当然ですが、実際にはすべての投稿を簡単に消せるわけではありません。削除請求が認められるかどうかは、書き込み内容が法律上の違法性を満たしているかどうかで判断されます。典型的には、事実無根の情報で物件や大家の社会的評価を下げる場合には「名誉毀損」、個人名や住所をさらされた場合には「プライバシー侵害」、虚偽の欠陥情報を広めて入居希望者を減らすような行為は「信用毀損」や「業務妨害」として対応が可能です。
具体的な流れとしては、まずサイト運営者やSNS事業者に対して削除請求を行います。それでも応じてもらえない場合、発信者を特定するために「発信者情報開示請求」を検討します。これはプロバイダ責任制限法に基づき、裁判所を通じてIPアドレスや契約者情報を開示させる手続きであり、権利侵害が明白であることが条件です。その後、発信者が判明すれば損害賠償請求も視野に入ります。
ただし、この一連の手続きには費用と時間がかかります。削除請求のみであれば数十万円程度で対応できることが多いですが、発信者情報開示から損害賠償請求まで進むと100万円を超えるケースも珍しくありません。期間も数ヶ月から1年以上を要するのが現実です。そのため「削除請求は可能か?」という問いに対しては、法的ハードルとコストを踏まえた上で判断すべきといえます。弁護士に相談することで、自分のケースがどの法律に当てはまるのか、どこまでの対応が現実的かを具体的に見極めることができます。とはいえ、残念ながら、ハードルが高く、費用倒れになってしまうことが多いのも事実です。
SNSトラブルに負けない「強いアパート」を作るための契約・管理術
SNSや口コミサイトでのトラブルを完全に防ぐことは難しいものの、契約や日頃の管理体制を工夫することで被害を最小限に抑えることができます。まず有効なのは、賃貸借契約書に「SNS利用に関する特約」を盛り込むことです。たとえば「事実に反する風評を意図的に流布し、物件やオーナーの信用を毀損する行為を禁止する」といった条項を明記しておけば、後に紛争となった際の抑止力や法的根拠になります。訴訟等になった場合に大きな効果が見込まれるかというと、少々厳しいものもあるのですが、「契約書に書いてある」というのは事実上の交渉の場面において、非常に有益です。
もっとも、入居者同士のSNS上での口論や誹謗中傷に、オーナーがどこまで介入するかは注意が必要です。過度に介入すれば「表現の自由の侵害」などと反発を招く可能性もあります。基本的には、他の入居者や物件の評価に直接影響を及ぼす場合に限定して、管理会社を通じて注意喚起や改善要請を行うのが現実的です。
また、法的な対応だけでは限界があります。日頃から入居者との信頼関係を築くことが、SNSトラブルの予防策として最も有効です。定期的な巡回や丁寧な管理対応、相談窓口を明確にしておくことで、入居者が不満をネットに書き込む前に直接相談してくれるようになります。結果として、物件のデジタル上の評判を健全に保ち、空室リスクを減らすことにつながります。オーナーにとって、ネット時代における「評判管理」は建物の維持管理と同じくらい重要な経営課題といえるでしょう。
法的措置は最後の手段。評判を守るための最善策とは
弁護士が本音をいうと、SNSトラブルを裁判所にて厳正に解決するというのは、正直難しい部分も多いです。法的ハードルが高いことに加えて、気軽に誹謗中傷の書き込みできるのに対して、裁判所・弁護士による対応コストが高額になってしまうからです。
そのため、いざとなれば弁護士・裁判所を頼るというわけではなく、そもそも悪い書き込みをされないように適正な管理と、賃借人・近隣住民との信頼関係の構築が重要と言えるでしょう。
<執筆者>
山村 暢彦
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。 数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。 相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。 クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。 現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。


