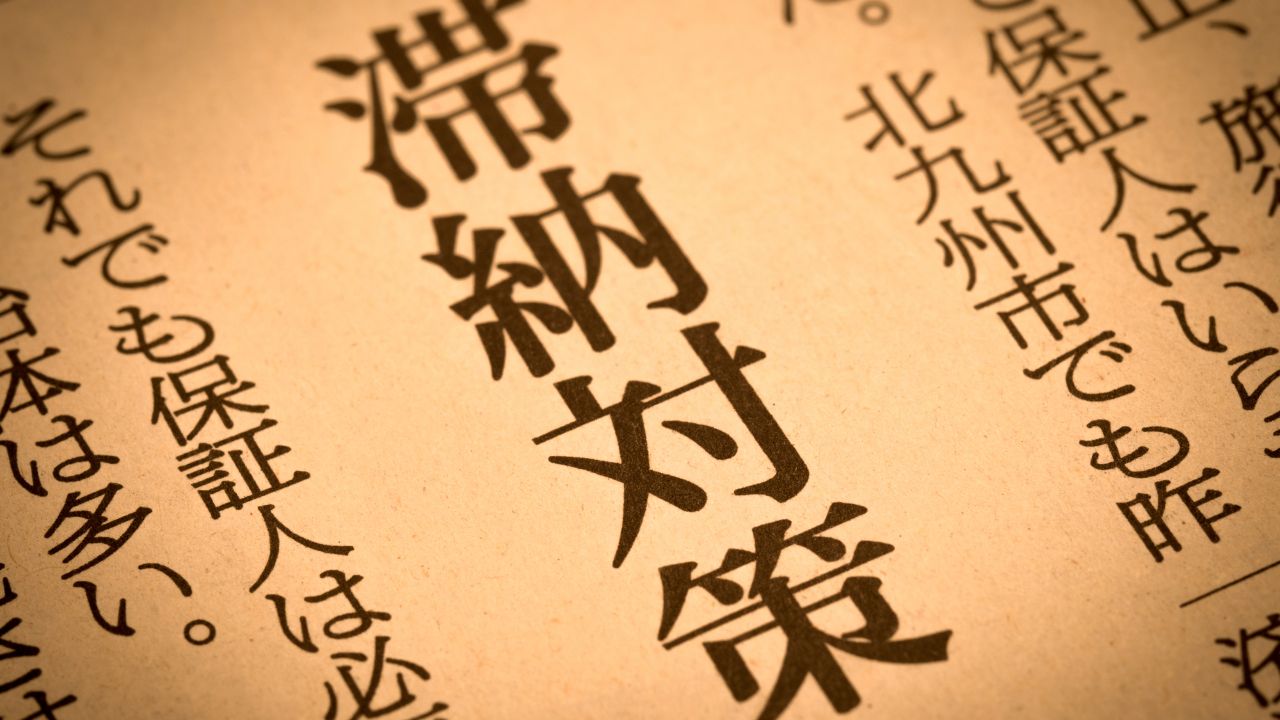
目次
家賃滞納は大家にとって大きな経済的負担となります。滞納が続く場合、どのように対応するべきか、回収のための法的手段について具体的に解説します。大家が知っておくべき回収方法や、法的な措置を取る際の注意点を紹介します。
ハウスリンクホームのLINE公式アカウントでは高利回り物件情報や資産形成のお役立ち情報を配信中です。
【LINE友だち登録はこちら】
家賃滞納の原因とその解決方法
家賃滞納の背景には、単なる「支払い忘れ」から「収入減少」「入居者トラブル」など多様な要因があります。
主な滞納原因としては、①一時的な資金難(ボーナス前など)、②失業・収入減少、③家族関係の変化(離婚・別居)、④入居者の高齢化や認知機能の低下、⑤入居者と管理会社・大家との信頼関係の悪化など、現実的な資金余力から生じる問題か、感情的なもつれなのかなど多様な要因が考えられます。
ただ、いずれのケースであっても、初動対応をスムーズに行うことが重要。滞納者への対応を放置しておくと、賃借人が「遅れても問題ない」と感じてしまい、しまいには居直ってくるようなケースが散見されるためです。
そのため、基本的な初期対応のポイントとしては、
(1)滞納発覚から3日以内に「書面+電話」で連絡を取る
(2)安易に「来月でいいです」と許容せず、「○日までの支払がなければ法的措置を検討します」と明確に伝える
といった督促、請求を迅速に行うこと。これらのアクションから、「家賃滞納を許さないぞ!徹底的に法的請求するぞ!」という態度を明確に示すことが必要です。
その後の対応としては、賃借人側の事情を丁寧にヒアリングし、場合によっては「分割払い合意書」の締結を検討したり、横着しているだけであれば少額訴訟等の法的措置を行ったり、相手の事情や態度に応じて柔軟な方策を考えていく必要があるでしょう。
もっとも、一般的には管理会社に依頼しており、賃料保証会社を利用しているケースが多いかと思います。そのため、賃料保証会社による補償が利用可能なケースなのかの確認、相談と、賃貸管理会社が放置せず督促するようにしっかりと監督するといった対応が大家側では必要な対応になってきます。
滞納賃料の回収方法と法的手段
任意回収が難しい場合、次のような法的手段が検討されます。
【ステップ1】まずは「内容証明」で正式に警告を送る
家賃を払ってくれない入居者には、まず「正式な手紙(内容証明郵便)」を出します。この手紙には、「○日以内に家賃を払ってくれないと、契約を打ち切って出ていってもらいます」という内容をはっきりと書きます。普通の連絡とは違い、証拠として残る郵便ですし、事実上、裁判提起する前に最終警告を送る際に送付するような郵便であるため、相手に対するプレッシャーになります。様式なども通常の便せんなどとは異なり本気感が伝わる体裁だと思います。「これは本気だな」と思わせることで、支払いに動くケースもあります。
ここまでは、賃料保証会社に切り替える前に、大家と管理会社で行っていくことが多い手続きかと思います。
【ステップ2】家賃を払わないままなら、裁判提起を検討する
それでも払ってもらえない場合は、賃料不払い理由として、立退請求という正式な裁判まで行うのか、賃料回収のみを目的として少額訴訟というやや簡易な手続きを利用するのかといった方針設定をしていきます。
相手の経済状態の変化等、支払いされることがまったく想定されない場合には、立退請求等を検討していくべきでしょう。他方、賃借人が横着しているだけとか、心情面の対立で支払わないといった状況であれば、賃料請求のみを目的に少額訴訟という手続きも検討可能。この手続きは、訴額60万円以下の場合限定で利用できる手続きで、1回の期日で決着を目指す手続きです。
このレベルの方針設定の段階までくれば、相談料がかかったとしても、不動産実務に詳しい弁護士に相談にいき、裁判手続きでできることできないこと、また、それに発生するコストなどを加味して方針設定すべきだと思います。少額訴訟の手続き自体は、大家自身でも利用できなくはないのですが、相手から反論がくると通常裁判に移行してしまうという側面もあり、複雑な状態にしてしまって後から弁護士に依頼すると、余計に弁護士費用が高額になるというケースも考えられるからです。
また、この段階からは賃料保証会社に裁判手続きや回収手続きの代行を依頼できるケースもありますので、初動対応でご説明したように、家賃滞納が生じた際には、賃料保証会社の規約の確認をしっかり行うべきといえるでしょう。
滞納解決後の入居者管理と再発防止策
いったん回収・明渡しが完了しても、同様のリスクは再び起こり得ます。そのため、最後に再発防止策についてお話ししま。まず、賃料保証会社の補償内容や契約内容も様々ですので、大家側にとって過不足のない補償内容かどうかをチェックすべきです。賃料不払いもある種「事故」ですので、予防のためには「保険」で備えておくほかありません。契約書の記載に穴があれば問題ではありますが、どれだけ厳重な契約書があっても、相手が不払いになった際には裁判の必要が生じてしまいます。そのため、予防策としては、賃料保証会社による補償内容の精査が重要だと思います。
もう一つは入居者の審査ですね。大家は、端的にいうと「嫌だ。」と思えば入居申し込みを断ることができます。空室リスクは回避したいとは思いますが、後からトラブルになりそうな入居者を安易に入居させてしまうことは避けて、入居者を精査すべきといえるでしょう。なお、ホテルや旅館等では、宿泊拒否できないケースがあるので、大家はこの点、「入居申し込みを断る権利がある」というのは、改めて意識されるとよいと思います。
————————-
賃料不払いはある種「事故」だと思いますので、大家業をやっている以上、いつ生じてしまうか予測がつきません。そのため、いざというときに備えて「保険」の見直しを行うとともに、トラブルが生じた際には、本記事を参考に「冷静に感情的にならずに」行動していただければと思います。
<執筆者>
山村 暢彦
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。 数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。 相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。 クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。 現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。


